■絵を描く数学「曲面結び目」で、「4次元空間」を理解するカギを発見!

理学研究科 数学専攻 博士課程3年 安田順平さん
目に見えない未知の空間「4次元空間」は一体どんな空間なのか、どうにかして視認できないか。そんな好奇心が安田さんの研究の原動力だ。
専攻分野はトポロジー(位相幾何学)。「図形の位置と形相を研究する幾何学」と呼ばれる。「パズルや図形を描くことが好き」な安田さんにぴったりの数学だ。
網膜という「面」を通して物を見る人間は、実は3次元空間すら直接知覚できていない。物体が重なったとき、その重なりの後ろに来る部分が見えないことから「奥行」があることを「認識」する。その意味で、「結び目」は3次元を表現できる単純な図形だ。
この結び目と同様に図形を視認することで4次元空間を直感的に認識しようと、先行研究で生み出されたのが「曲面結び目」だ。安田さんは「曲面結び目」を「結び目の時間変形」と解釈。一つの図形ではなく、時間の流れとともに「結び目」が変化する様子全体を示すことで、4次元空間を把握できないかと試みた。
そこで、3次元空間を表す「結び目」に加えて、さらに「組み紐(ブレイド)」という垂れ下がる複数の紐を編んでできる図形を抽象化した概念に注目。安田さんは「プラット閉包」という「組み紐(ブレイド)」を「結び目」に変換する手法を応用し、4次元空間を表示する新しい「曲面結び目」のパターンを開発した。これは、4次元空間を理解する新たな鍵を手にしたといえる快挙だ。この成果は高く評価され、国内外で様々な賞を受賞した。「曲面結び目を表示するツールを開発できた。今後、誰が見てもそれが4次元空間を表現していると分かる理論を形作りたい」。謎多き4次元空間がその姿を現す日も近いかもしれない。
ロングインタビューは こちら
■ネイティブが説明しづらいことほど面白い!フランス語の前置詞を通して見える「世界」の捉え方

言語文化研究科 言語文化専攻 博士課程3年 梶原 久梨子 さん
「明日は娘の誕生日だった!−誕生日は未来のことなのに、なぜ過去のことのように話すのか?」学部時代の授業で出会った問いが、梶原さんが言語学に興味を持つきっかけとなった。「フランス語でもそのような場合は過去形を用いると知り、日本語とかけ離れた言語でも時間を同じように捉えることがあるのか、と驚いた」。
言語には、その言語を話す文化特有の時間や物事の捉え方が反映される。ならば、言語を手がかりにすれば、その言語の話者が世界をどのように捉えているかを理解できるのでは?と考え、言語学者を志した。
フランス語で「無色透明」といわれるほど汎用性の高い前置詞àとdeの意味を取り出すことを目的とし、様々な構文におけるàとdeの機能を研究。まず着手したのは、「続ける」を意味する動詞continuerに続くàとdeの使い分けだ。ネイティブも「好みの問題」としか答えられないこの命題に、大量の言語データを分析するコーパス調査や、フランス語母語話者に文の容認度を尋ねるインフォーマント調査などを用いて挑んだ。àは話し手の主観的な評価が含まれるとき、deは話し手が中立的に伝えるときに使われることを見出した。「世界の捉え方という目に見えない問題に対し、言語学の立場から一つの答えを出せたと思う。ネイティブが論理的に説明できない問題こそ、言語学者が研究する意義がある」。
研究の傍ら、非常勤講師としてフランス語の授業を行う。「フランス語話者の世界の捉え方を研究する」言語学者として、言語の背景にあるフランス語話者の考え方や時間の捉え方なども伝える。「今までの語学の授業とは違う視点でワクワクする」と学生からの反応は上々だ。春からは言語学の知見を取り入れ、教育開発の分野でアカデミアの道を進む。
ロングインタビューは こちら
■ VR技術を駆使して「恐怖体験」の脳内メカニズムに迫る。
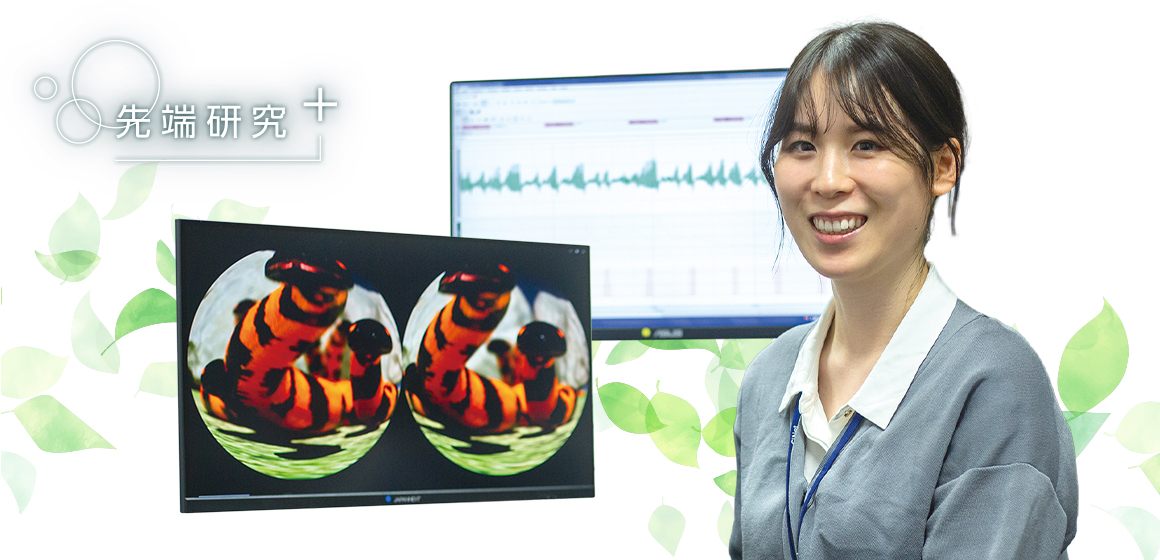
生命機能研究科 生命機能専攻 博士課程2年 藤野美沙子さん
我々は、ヘビやクモ、高所など、日常におけるさまざまな対象に恐怖を感じる。この時、脳で何が起こっているのか、どうすれば恐怖を抑えることができるのか――藤野さんは、脳活動を非侵襲的に計測できる「fMRI」と、仮想現実(VR)を組み合わせた画期的な手法を用いて解明を試みている。具体的には、被験者にヘビやクモが間近に迫ってくるVRを体験してもらい、脳の血流により生じる「BOLD信号」を計測した。「脳活動の変化を解析することで、三次元のVR恐怖環境でより強く活動する脳領域が明らかになりました。今後は、三次元空間における奥行き知覚や臨場感が脳でどのように表現されているのか、これらの知覚が恐怖感にどう影響するのかというメカニズムの解明に挑みたいです」。これまでに、高所恐怖反応の抑制に関する研究も展開。VRや脳機能イメージング技術を用いた基礎研究が恐怖症の治療法の発展に役立つ可能性もあると話す。
活動は所属研究室にとどまらない。ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムの9期生として、研究科を超えた学生チームで「脳情報から感情を解読するための深層学習モデル」の融合研究を進める。また、自然科学系女子学生による組織「asiam(アザイム)」の一員として小学生向けワークショップの講師を務める中で、アウトリーチへの想いも芽生えた。「いつか小中学生向けの本を書いて、心と脳の仕組みを探求する研究に興味を持ってもらえたら」。研究活動を楽しみ、没頭する先に、いつも人の存在がある。藤野さんの研究者としての姿勢がうかがえた。
ロングインタビューは こちら
(本記事の内容は、2025年2月発行の大阪大学NewsLetter 92号に掲載されたものです)
のびやかでひたむきな阪大生の物語『 きらめきのStoryZ 』に戻る
阪大研究者、阪大生、卒業生の物語『 阪大StoryZ 』に戻る
