
最先端の「ワクチン療法」を牽引
がん治療用ワクチンを含め、がんの新薬の実用化に向けた臨床研究に挑んでいる中村教授。「がんゲノム・個別化医療研究」で知られる世界的権威だ。2012年4月、シカゴ大学医学部の内科・外科教授として迎えられ渡米した。「今の日本では新薬の開発や実用化が難しいと、悩んだ末の決断だった」と中村教授。現在は「年に5〜6回ほど、3泊5日や4泊6日の短い日程で日本に帰国し、縁ある学会から依頼された講演などを行っている」と話す。
今、がん治療の分野では、がん特異的ワクチンなどを含めた患者本来の免疫力を高め、がん細胞の増殖を抑える「免疫療法」が、外科療法・化学療法・放射線療法に次ぐ「第4の治療法」として定着しつつある。科学的検証が可能で、従来の抗がん剤のような副作用が少なく、世界から注目されている最先端治療だ。また、中村教授は昨年秋、がん細胞を狙い撃ちする分子標的薬の新しい有力候補となる化合物を発見したと、米国の医学誌「サイエンス・トランスレーショナル・メディシン/Science Translational Medicine」に発表。来年をめどに臨床試験が始まる予定で、世界中から問い合わせが相次いでいる。
適切な時に適切な治療を
中村教授は、かねてより、薬をより安全に効果的に提供する「オーダーメイド医療」を提唱してきた。「現在は『プレシジョン・メディシン/Precision Medicine』と表現されることが多いですね。なじみのない言葉だと思いますが、意図するところはオーダーメイド医療と同じ。これまでのような画一的治療ではなく、個々人のゲノムの個性などを考慮した予防や治療を確立しようというもの。今年1月、オバマ大統領が一般教書演説の中で『プレシジョン・メディシン・イニシアティブ/Precision Medicine Initiative』に関する詳細を発表するなど、適切な時に適切な治療を患者さんに提供する医療が米国などで始まりつつあります」
抗がん剤などは、最新の薬であっても効かない人も多く、がんは、そのプレシジョン・メディシンが求められる最も重要な分野だ。しかし、がん治療のプレシジョン・メディシンに「日本だけが旧態依然の体制で取り残されている」という。
最後まで希望を提供したい
日本と米国の医療には驚くほどの格差がある。「一番大きな違いは、がん患者に、どこまで希望を提供できるかですね。例えばシカゴ大学では、年間200種類ほどのがんに関する臨床試験が始まり、沢山の新しい治療法が提示されますが、日本では標準治療に終始し、患者さんは新しい治療へのアクセスが非常に限られています。そしてマニュアルに沿ったがん治療が行われ、保険適用の薬が尽きると余命宣告が行われる。私は、それは真っ当な医療ではないと思っています。医者である以上、患者さんに最後まで希望を提供したい。仮に命が尽きたとしても、ご本人や家族が、世界で最先端の治療を受けることができた、ここまでやったのなら仕方がないと納得でき、悔いを残さないような医療体系を作らないといけない」
メディアもリスクに対する理解を
医療に関するメディアや社会の考え方、受け止め方も、日本と米国では大きく異なるという。「治すことが難しい病気を治そうとするにはリスクが伴います。しかし何も治療しなければ患者さんは確実に死に向かっていきます。そんな目の前の患者さんや家族の切実な思いに応えようとしたチャレンジが、経過を評価することなく情緒的な批判の形で報道されてしまう。一定の根拠に基づいているが未だ確立していない治療法について、メディアや社会が理解し受け入れない限り、日本から新しい医療は生まれないと思います」
さらに、米国と日本では研究者の意欲や姿勢などにも顕著な差を感じている。中村教授のシカゴ大学の研究室には現在、10か国からの研究スタッフが所属しているが、「日本人は明らかに気迫に欠けています。日本以外の国から来ている人たちの場合、将来は母国に貢献したい、あるいは米国で生き残り社会に貢献したいという意欲が強い。しかし日本からの研究者の多くは、帰国後のポジションが担保されており、ここで生き延びなくてはならないという気概が感じられません」と苦言を呈したうえで、「留学して頑張れば、人脈などがなくても、帰国後は良いポジションにリクルートされるといった正当な評価制度を機能させ、若手の活性化を図る必要があると思います」と訴えている。
重き荷を負うて遠き道を往く
中村教授の研究分野は遺伝学・腫瘍学だが、もともとは大阪大学医学部附属病院第2外科などで外科医を務めていた。医師を志したのは「中学2年の時、スキーで足の骨(大腿骨、脛骨、腓骨)を折って3カ月間の入院を余儀なくされ、治療にあたってくれた医師の姿を見て憧れを持ちました。ちょうどその頃、祖父と叔父を立て続けにがんで亡くすという体験も重なり、医学部への進学を決意しました」
 その後、メスを試験管に持ち替えて医師研究者の道へ。「若い時から手術が好きで、自分が研究者に向いているとは全く思っていませんでした。しかし堺の市民病院で外科医をしている時、若いがん患者さんを続けて看取ったのです。がんを告知しない時代でしたから、患者さんと医師は、言わば、あうんの呼吸で日々を過ごしているわけです。しかし徐々に症状が悪化するなかで、患者さんが辛さに耐えかねて私の白衣をつかみ、お腹のを取ってくださいと泣き叫んだのです。言葉が出なかったですね。そのような経験もあって、若くしてがんになる遺伝性大腸がんに興味を持ち、まずユタ大学(米国ユタ州)ハワード・ヒューズ医学研究所の門を叩いて遺伝学の研究を始めました。5年ほどで世界でも名を知られるようになり、この研究で多くのがん患者さんに貢献できるのではないかと考えてメスを捨てました」
その後、メスを試験管に持ち替えて医師研究者の道へ。「若い時から手術が好きで、自分が研究者に向いているとは全く思っていませんでした。しかし堺の市民病院で外科医をしている時、若いがん患者さんを続けて看取ったのです。がんを告知しない時代でしたから、患者さんと医師は、言わば、あうんの呼吸で日々を過ごしているわけです。しかし徐々に症状が悪化するなかで、患者さんが辛さに耐えかねて私の白衣をつかみ、お腹のを取ってくださいと泣き叫んだのです。言葉が出なかったですね。そのような経験もあって、若くしてがんになる遺伝性大腸がんに興味を持ち、まずユタ大学(米国ユタ州)ハワード・ヒューズ医学研究所の門を叩いて遺伝学の研究を始めました。5年ほどで世界でも名を知られるようになり、この研究で多くのがん患者さんに貢献できるのではないかと考えてメスを捨てました」
中村教授は自身を織田信長タイプと評する。実際、過去には血の気の多さを示すエピソードもある。大阪の府立病院に勤務していた時代、刺されて救急搬送されてきた暴走族の患者の治療をめぐり、オートバイを吹かして騒々しく乗り込んできたリーダーと、外来で怒鳴り合ったこともあった。しかし、「最近は少し人間が丸くなりました(笑)」。また、研究成果に関する「がん患者の強い期待」といったプレッシャーなどもあり、「人の一生は 重き荷を負うて遠き道を往くが如し」という徳川家康の言葉に共感している。
がんという病気にリベンジする
実は研究者としての中村教授には、研修医時代から肩に重くのしかかっている出来事がある。一人の胆石患者が、手術後、昼夜を通しての懸命な措置にも拘わらず脳死となった。「患者さんの奥さんは『一生懸命にやってくださった姿を見ているので…』と、事を荒立てることなく、 『どうか良いお医者さんになってください』と、無念さをこらえて私に言ってくださいました。その奥さんの言葉は決して忘れることはできません」とかみしめるように語る。
さらに、母親を大腸がんで亡くした体験が、中村教授の研究者としての人生を支えている。
「母は私が大腸がんの研究で成果を上げてきたことを知っていたので、自分が大腸がんにかかったことを、『おまえに恥をかかせて申し訳ない』と謝りました。この言葉は私の胸に突き刺さりました。そして亡くなるまでの、痛みに耐えている顔や浮腫で腫れあがった足などを見ていて、自分の研究の無力さを痛感し人生観が変わりました。患者さんに貢献できなければ医学研究でないとより強く思うようになりました。以来、日本人の3人に1人が命を落とすがんという病気にリベンジするという気持ちが私の支えになっています。自分が作った薬でがんが消えて、患者さんが元気で帰っていく。その姿を見るまで人生の目標を達したとは言えません」
今後の去就については、「日本という国が好きですし、日本のためになる何かができるのであれば、帰国し貢献したい気持ちはあります。しかしシカゴ大学で学んだことを海外からの眼で日本に伝えることも大事な役目ですし、何より大切な視点は、自分がどこで研究すれば一番患者さんの役に立てるかだと思います」
「医療は実学」、患者に何ができるか
学生の頃、山村雄一先生や曲直部寿夫先生の講義を聞いて感銘を受け、「自分もこういう医者になりたい」と強く思ったという。その後も恩師に恵まれ、医師としてのキャリアを積んでいった。一方で、若い人を育てる難しさも感じているという。
医師をめざして医学部で学ぶ後輩には、「漫然と研究するのではなく、患者が何に苦しみ、医者や医療に何を求めているのかを、日々の臨床現場でつかみ取れる医者になってほしい。医療というのは『実学』です。患者さんのために何ができるか、目の前の患者さんをどうしたら救えるか、緒方洪庵のような視野を持った医療、それが医師人生を通じて一番大事な課題。自分がこの患者さんに行った治療はベストなのかどうか、もっとしてあげられることはないのか、日々自身に問いながら、一方で学問を追究して、さらに良い治療ができるよう取り組んでほしい」と自身の信念に重ね合わせて呼びかける。「研究成果に対する受賞などは結果であり、決して賞を求めるような医者にならないでほしいですね」とも。阪大生を含む若い世代に対しては、厳しさを込めながらも力強いエールを送る。「すごく視野が狭いような気がします。日本という国に誇りを持ち、日本が、そして自分が世界で何をできるのか、考えていってほしい」と締めくくった。
■ 中村祐輔(なかむら ゆうすけ)氏
1977年大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部附属病院や関連施設の外科勤務を経て、84〜89年ユタ大学ハワードヒューズ 研究所研究員、医学部人類遺伝学教室助教授。89〜95年㈶癌研究会癌研究所生化学部長。94年東京大学医科学研究所分子病態研究施設教授。95〜 2011年同研究所ヒトゲノム解析センター長。05〜10年理化学研究所ゲノム医科学研究センター長(併任)。11年、内閣官房参与内閣官房医療イノベー ション推進室長。12年4月から現職。
◎西尾総長 懇談を終えて

中村祐輔先生とは政府系の委員会等でしばしば隣の席に(五十音順で席が並ぶ)座っていました。久しくお会いしていませんでしたが、今回奇しくもGlobal Alumni Fellowの称号をお渡しする機会を得ました。型にはまらない豪快さと先見性は変わらないとの印象でした。医学・医療への真摯な思い、特に病気に苦しむ患者さんに希望を与えたいという強い信念には改めて敬服いたします。「大阪には阪大を始め研究機関や病院など医療の拠点が集積している。このメリットを活かしたオール大阪の医療体制を作れないか」「阪大が有する先端医学や医療情報と、(西尾総長の専門の)データ工学、データ解析技術などが連携した取り組みが学内でもっとできるのでは」といったご提案に視野の広さを感じました。大阪大学総長として何ができるか改めて真剣に考えてみたいと思います。中村先生にはグローバルに活動してほしいと思う一方で、これからは母校阪大のためにもご助言いただけたらと思っています。今回、大変有意義な懇談ができたことを感謝するとともに、ご活躍を祈念しております。
Osaka University Global Alumni Fellow
大阪大学では、教育・研究の国際的なネットワークづくりの一環として、本学の卒業生や元教職員で、海外の大学・研究機関等で活躍される方々を対象に、栄誉な称号として「 Osaka University Global Alumni Fellow」を創設。これまでに17名に授与している。

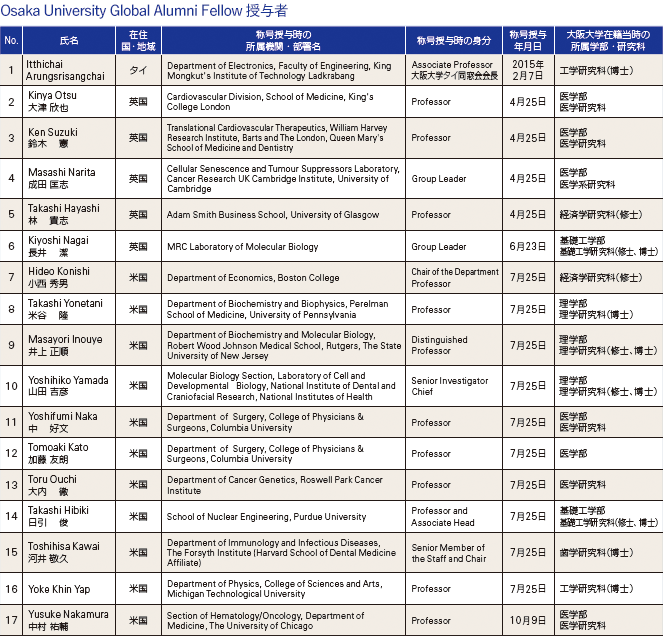
(本記事の内容は、2015年12月大阪大学NewsLetterに掲載されたものです)
