ただの書籍紹介を「おもしろく」
「書評対決」は全学教育推進機構の松行輝昌准教授と中村征樹准教授のほか、附属図書館や生活協同組合書籍部の担当者が企画し、生協書籍部主催で今年4月にスタート。「活字離れ」が言われて久しい学生たちに良い本を紹介するだけでなく、教員にも「読む側の視点」を持ってもらうのが狙いで、単なる書籍紹介ではなく、教員と学生が同じ土俵で勝負する面白さを取り入れた。
書評を書くメンバーは月ごとに替わる。学生側はこれまで「サイエンスルー」「漂流記」「ショセキカ」など文芸サークルや学生団体が参戦。6月の第3回までは学生が連勝、夏以降は教員側がリベンジを果たし、好勝負を展開している。
「学生の書評のクオリティーが予想以上に高い。私たちが知らなかったような本を出してくることもあり、文章もウイットに富んでいて感心します」と松行准教授。学生グループにとっては、活動が多くの人の目に留まり、同人誌が改めて注目されるなど、新たなつながりが生まれるきっかけにもなっているという。第1回の教員側で〝敗戦〟した中村准教授は「さらっと負けてしまい、悔しかった」と苦笑しながらも「教員の皆さんも楽しんで参加してくれている様子。あの人はこんな本が好きなんだという新鮮な驚きもあります。O+PUS動画でも紹介され、楽しい企画に育っていてうれしい」と話す。
紹介本や書評は、生協の豊中書籍ショップ、工学部書籍ショップ、総合図書館、理工学図書館にあるほか、Webでも紹介。毎回10冊分を掲載した書評集も好評で、ショップの特設コーナーへのリピーターも増えている。教員、図書館、生協が部局を超えてつながり、学生を交えて展開される熱いバトルから、今後も目が離せない。
Book Collection 11月 対決
教員
「発想の転換してもらえる本を」 ─坂尻彰宏准教授
 11月の書評を書いた坂尻彰宏准教授(全学教育推進機構)は「まず手に取りやすく、驚きや謎解きの面白さ、発想の転換を経験してもらえるような本を選びました。学問をする上でも重要なファクター。まずは面白さを味わって」とアドバイスする。日ごろ慣れている論文と違い「書評を書くのは難しい。O+PUSで自分が出ている動画が流れるのも、実は恥ずかしい」。学生には「開けばそこに発見がある」読書の素晴らしさを伝えたいという。
11月の書評を書いた坂尻彰宏准教授(全学教育推進機構)は「まず手に取りやすく、驚きや謎解きの面白さ、発想の転換を経験してもらえるような本を選びました。学問をする上でも重要なファクター。まずは面白さを味わって」とアドバイスする。日ごろ慣れている論文と違い「書評を書くのは難しい。O+PUSで自分が出ている動画が流れるのも、実は恥ずかしい」。学生には「開けばそこに発見がある」読書の素晴らしさを伝えたいという。
学生
「人生論から柔らかい読み物まで」 ─読書会Liber
 対する学生側は「読書会Liber」。2013年秋に発足、ニーチェなど「普段読まない本」を取りあげて読書会をする硬派のサークルだ。今回は5人のメンバーが各自の個性を出そうと選んだ結果、人生論から柔らかい読み物までと分かれた。「書評を書くのはいいアウトプットになる」(経済学部2年・田嶋直輝さん)、「先生が薦める本もぜひ読みたい」(同・徳永惇士さん)と意欲的だ。
対する学生側は「読書会Liber」。2013年秋に発足、ニーチェなど「普段読まない本」を取りあげて読書会をする硬派のサークルだ。今回は5人のメンバーが各自の個性を出そうと選んだ結果、人生論から柔らかい読み物までと分かれた。「書評を書くのはいいアウトプットになる」(経済学部2年・田嶋直輝さん)、「先生が薦める本もぜひ読みたい」(同・徳永惇士さん)と意欲的だ。
書 評
書評対決で最も阪大生に読まれた本と書評をご紹介
◉ 『はじめての構造主義』 ─(8月教員側登場:附属図書館・久保山 健)
 「自動車の発明は、自動車"事故"の発明」と、同じ分野で注目された浅田彰がかつて発言したと記憶する。しかし、2011年3月の重大な事故で、そのような考えを持っていた人が、どれほどいただろうか。「構造主義」と聞いてもピンとこないかもしれないが、本書は近代的な「進歩」だけでなく、多様な価値観、見方を得る枠組みを、平易な記述で解説してくれる。
「自動車の発明は、自動車"事故"の発明」と、同じ分野で注目された浅田彰がかつて発言したと記憶する。しかし、2011年3月の重大な事故で、そのような考えを持っていた人が、どれほどいただろうか。「構造主義」と聞いてもピンとこないかもしれないが、本書は近代的な「進歩」だけでなく、多様な価値観、見方を得る枠組みを、平易な記述で解説してくれる。
私たちは、進歩は善いことと思い、自分の尺度で他の人や社会を評価しがちである。本書から、違う角度でものごとを見るきっかけを得られるだろう。
「現代を読むカギ、二十一世紀を読むカギがここにあります」(p.5)と述べる本書が発行されてから26年。地域紛争、南北格差、科学技術の社会的意味、出生前診断など、社会はより複雑になっている。だからこそ、本書から、ものごとを多面的に考えることを改めて振り返ってはどうだろうか。少しでも興味を感じたら、20ページほどの第1章「『構造主義』とは何か」だけでも読んでみよう。20世紀以降の考え方の流れと、構造主義の立ち位置が大まかに理解できる。
◉ 『酒とつまみの科学』 ─(6月学生側登場:ショセキカプロジェクト)
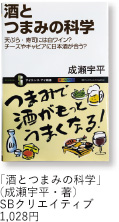 大学っていいところ、だって先輩がいろんなお酒を教えてくれる。ビール、カシオレ、ハイボール、ちょっと飲めるようになったら日本酒に焼酎。どのカクテルが飲みやすいか、どの割り方がおいしいか、たぶんほとんどの人が、大学入ってお酒に詳しくなったのではないでしょうか。そう、あくまで“お酒”に─。この本は、普段「枝豆」や「フライドポテト」に染まっている人たちにぜひ読んでほしい一冊です。みなさん、“おつまみ”について、何か説明できますか? なんでもいいです。例えば「肉には赤ワイン」なんて言いますが、なぜ白ワインじゃダメなのでしょうか。魚や鶏料理にレモンをかけるのはなぜなのでしょうか。
大学っていいところ、だって先輩がいろんなお酒を教えてくれる。ビール、カシオレ、ハイボール、ちょっと飲めるようになったら日本酒に焼酎。どのカクテルが飲みやすいか、どの割り方がおいしいか、たぶんほとんどの人が、大学入ってお酒に詳しくなったのではないでしょうか。そう、あくまで“お酒”に─。この本は、普段「枝豆」や「フライドポテト」に染まっている人たちにぜひ読んでほしい一冊です。みなさん、“おつまみ”について、何か説明できますか? なんでもいいです。例えば「肉には赤ワイン」なんて言いますが、なぜ白ワインじゃダメなのでしょうか。魚や鶏料理にレモンをかけるのはなぜなのでしょうか。
世の中にあふれる“酒の友”について知らないなんてもったいない! それならば、と科学的根拠にちょっぴり作者の好みを混ぜて紹介してくれるのがこの本です。
合コンで使える雑学本として、というよりもうレシピ本として、ぜひ手元に。
【評:工学部環境・エネルギー工学科 平野雄大】
学内全学ディスプレイシステム「O+PUS(オーパス)」
 学内の食堂や図書館、学内バスの停留所など全キャンパスの26か所に設置。学生がコンテンツ制作に参加するものや、フルハイビジョンによる高精細な画像を使ったコンテンツなど、学生が興味を持ち、積極的に参加したくなるコンテンツを放映。ブックコレクションCMも、「対決」の要素をクローズアップしたユニークな内容で話題を呼んでいる。
学内の食堂や図書館、学内バスの停留所など全キャンパスの26か所に設置。学生がコンテンツ制作に参加するものや、フルハイビジョンによる高精細な画像を使ったコンテンツなど、学生が興味を持ち、積極的に参加したくなるコンテンツを放映。ブックコレクションCMも、「対決」の要素をクローズアップしたユニークな内容で話題を呼んでいる。
大阪大学公式You Tubeでも公開。
(本記事の内容は、 2014 年 9 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)
