
ヘルスケアからエンターテイメントまで! 「オートフォーカスグラス」が切り拓く 「メガネが目をケアする」新時代
株式会社エルシオ 代表取締役 李蕣里(り・じゅんり)
「メガネ」は今や多くの人に必要不可欠だ。年齢を重ねるにつれ悩まされる老眼や、発症の低年齢化が進む近視。高齢者の白内障や子どもの小児弱視など、生活や治療にメガネを必要とする病気も多い。一方、VR(仮想現実)など、メガネを通して楽しむエンターテイメントも近年人気を博している。
大阪大学発のスタートアップ「株式会社エルシオ」は、特殊なレンズがその人の見え方に応じて自動でピントを合わせるメガネ「オートフォーカスグラス」の開発を進めている。李蕣里代表取締役は、ヘルスケアからエンタメまで幅広く役立つ「夢のメガネ」の実現に向け奮闘している。
「フレネル液晶レンズ」が起こすメガネレンズ革命
「オートフォーカスグラス」のベースとなるのが、エルシオが開発した「フレネル液晶レンズ」だ。
液晶レンズは、多数の液晶分子が透明な基板の内部に封入された特殊なレンズで、電圧をかけると液晶分子と同時に内部を通る光の曲がり方が変化する。電圧をうまく調整すれば、様々な度数を実現することが可能だ。しかし、小さく分厚くて視野が狭いため、メガネレンズには適さない。そこで、同心円状の電極を透明基板上に貼り巡らせることで、レンズの厚みを減らすと同時に大口径化を可能とするフレネルレンズの設計思想を取り入れた。これにより、液晶レンズの口径を大きく、薄くし、さらに度を強くする「三つの利点」を得ることに成功した。
現時点での開発製品はおよそ30ミリ口径で、度数は「ある程度の老眼に対応できる」という±2度程度まで実現。今後さらに口径の大きさ、度の幅を広げる方針だ。
メガネのフレーム内部には電池や集積回路を搭載し、それを駆動させることで電圧を調整しピントを合わせる。「1台のメガネの視野全面で適切な距離に合わせられる」ため、近視・老眼の進行や目の病気の治療に伴うメガネの掛け替え、買い替えは不要になる。
エンターテイメント分野での活用も

自動でピントを合わせる“オートフォーカス”の前段階として、まずは、スマホ操作で度数調整が可能なメガネのプロトタイプを作製した。現在、センサーをフレームに搭載し、対象との距離に応じて焦点を合わせるタイプの開発を急いでいる。「早ければ2026年半ばごろまでに製品化し、一般向けの販売を実現したい」。さらに、目の動きをセンシングし、見え具合まで含めて検証する方法を、大阪大学大学院情報科学研究科の前田太郎教授の研究室とともに進めている。
「大きなサイズの、度が変わるレンズを作れるのが弊社のコアテクノロジー。これは、スマホ・PCディスプレイや顕微鏡、通信用など幅広い用途がある」。実際、VRなど、現実とデジタルを同時に体験できるXR(クロスリアリティー)用のグラスの製造企業から引き合いがあり、レンズのサンプル販売を始めた。李氏は「誰がかけても度が合い、機能がたくさん載り、分厚さや重たさを避けたいという企業側の現在の要望に応えることができます」と、取引の本格化に期待を寄せる。
小児弱視の女の子との出会い
李氏はもともと、大阪大学大学院理学研究科の博士課程で、有機合成アプローチによる電子材料の研究を行っていた。ちょうどその頃、工学研究科の特任研究員としてフレネルレンズの開発に取り組んでいた澁谷義一さんとアントレプレナーシップ講座で出会う。「基礎研究だけで終わるのはつまらない、自分で何かを切り開きたい」と考えていた李氏は、液晶レンズに強く惹かれた。これが起業の契機になった。
レンズはメガネに使えるのでは?と考え、社会実装に向けた調査として、大阪大学医学部附属病院で患者たちに話を聞くことに。その時、心に響く出会いがあった。小児弱視で知的障がいもあり、意思の疎通ができない女の子。小児弱視の治療には正しい度数での矯正が必要だが、意思疎通が難しければ度数が合っているか確認のしようがない。母親は涙を浮かべて将来を心配していた。「本人が伝えられなくても、オートフォーカスならレンズが合わせてくれる。苦しんでいる人のためにもそんなメガネを作りたい」。そう決意し、澁谷さんとともに液晶レンズの研究に打ち込んだ。19年、2人の共同でエルシオを創業。現在、8人のメンバーがいる。
大阪・関西万博でも訴えたい、「目のケア」の大切さ
エルシオは25年4月に開幕する大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンへ出展する。「出るチャンスがあるのに、応募しないなんてあり得ない!」と、迷わずトライした。オートフォーカスグラスのプロトタイプのほか、白内障などの視覚障がいを体験できるVRシステムも用意する。目のケアの大切さとともに「より多くの人に自社技術を知ってほしい」と意気込む。
現在、技術開発に向けた資金調達に加え、製品化にかかる製造の形態やコストなど検討課題は多く、奔走する毎日だ。焦りや不安がないわけではないが、「見え方」で困っている人たちの力になりたい、との思いが活動を支える。「老眼や弱視だけでなく、近視の進行を止めたり、ひどい眼精疲労を調整したりできるようになれば」。2050年には病的近視などで10人に1人が失明するという予測データもあるといい、「そういうことを防ぐためにも、目のケアの意識を広めたい」と願う。
■ 李蕣里(り・じゅんり) プロフィール
大阪大学理学部化学科を卒業後、東京大学大学院理学系研究科化学専攻(修士)を経て、大阪大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程を2017年に修了。博士(理学)。大阪大学大学院工学研究科で特任助教などを務め、19年にエルシオ創業、20年副社長に就任。21年から現職。
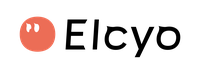
■株式会社エルシオ Webサイト https://elcyo.com/
(※ 本記事は、2025年2月発行の大阪大学NewsLetter 92号に掲載されたものです。 )